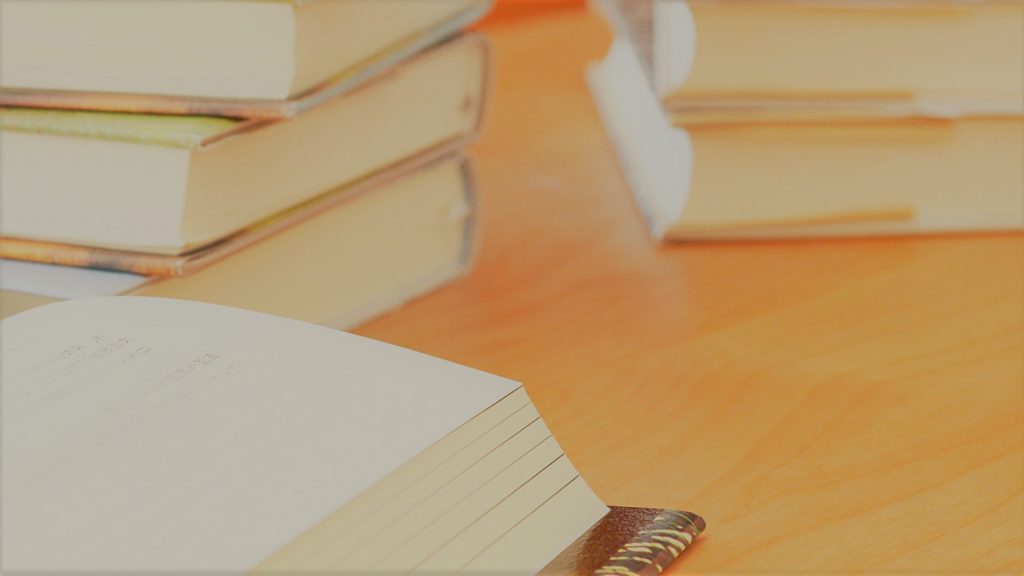
書籍のご紹介です。
著書:SDGsの主流化と実践による地域創生-まち・ひと・しごとを学びあう -
著者:樋口 邦史 編
出版年月日:2019年6月15日
出版社:水曜社
ISBN: 9784880654645
概要:
本書は、近年、政府の地方創生施策に基づき展開されているような「まち・ひと・しごと」の視点から、持続可能なまちづくりの在り方を検討したものである。とくに、SDGsの観点を取り入れつつ、全国で展開される「まち創り」の事例が検討されている点が特徴である。例えば、「イノベーションをおこすまち創りの倫理」として、リビングラボ、キリン株式会社、北海道白老町等の事例が、「子供たちと実践するみらい創り」として、教育改革やスポーツ、アート等の事例が、「稼げるまち創りに向けたカレッジ進化論」として、研究開発思考、エコシステム、食育カフェ、等の事例が、「地域のしごと創りを支える資源価値評価とその展開」として、遠野木工団地の木材産業クラスターが、そして、「企業の“みらい創り”に必要な戦略と評価方法」として、コンプライアンス・マネジメント、攻めのCSR経営、社会的インパクト評価等についての検討が行われている。現実的かつ協働的なまち創りを考えるうえで多くの示唆に富んでいる。
http://suiyosha.hondana.jp/book/b451769.html
日本全国で行われる「まちづくり」事業。しかし旗振り役の交代や引退、企業や大学の撤退などにより、継続的な活動は困難であること多い。産官学民のニーズが乗じる形での協働的な実践活動を継続させていくためにはどのようなリーダーシップやコーディネート力が必要なのか。それはどう実行され「まち・ひと・しごと」創りには、どのような創意工夫が必要なのか。
それには自立した民間が現状認識に基づいた持続可能な社会を生み出す新たな目標を掲げつつ、ビジネス(=稼ぎ)創造に真剣に向き合うこと。そして行政が、規制緩和や地域を越えた協力関係を強化しながら、現実的で協働・協調的な事業を作り出していくこと。この両輪の活動が効果的且つ継続的に回ることが重要である。
本書では「まち」創りの論理と、それに不可欠な「ひと」創りの実践活動に焦点を当て、更に交流・連携し実践される「しごと」創りの事例を行政と研究者の視点で記述。地域社会がどのように協働しながら生業を創造するための具体的な方法と、企業が組織的にCSRや「みらい創り」活動を進める上で必要な戦略とその評価方法を示した。
産官学民のプロジェクト的な活動として実践的な協働作業へと発展した「遠野みらい創りカレッジ」。その活動は神奈川県南足柄市、北海道の白老町、長崎県の壱岐市、そして山梨県の都留市などへ広がり、地域の若者を中心に産官学民との交流から共通価値を創出し、多くの地域のリーダー的人材が輩出されている。「まち・ひと・しごと」創りから、継続的なまちづくり事業を実現するための最新刊。
目次:
序章
住み続けられる「まち」を支える「ひと」「しごと」の創造
1章 イノベーションを起こす協働のまち創りの論理
2章 次世代を担う子供たちと実践するみらい創り
3章 稼げるまち創りに向けた“カレッジ進化論”
4章 地域のしごと創りを支える資源価値評価とその展開
5章 企業の“みらい創り”に必要な戦略と評価方法
文責:小田切康彦(徳島大学)